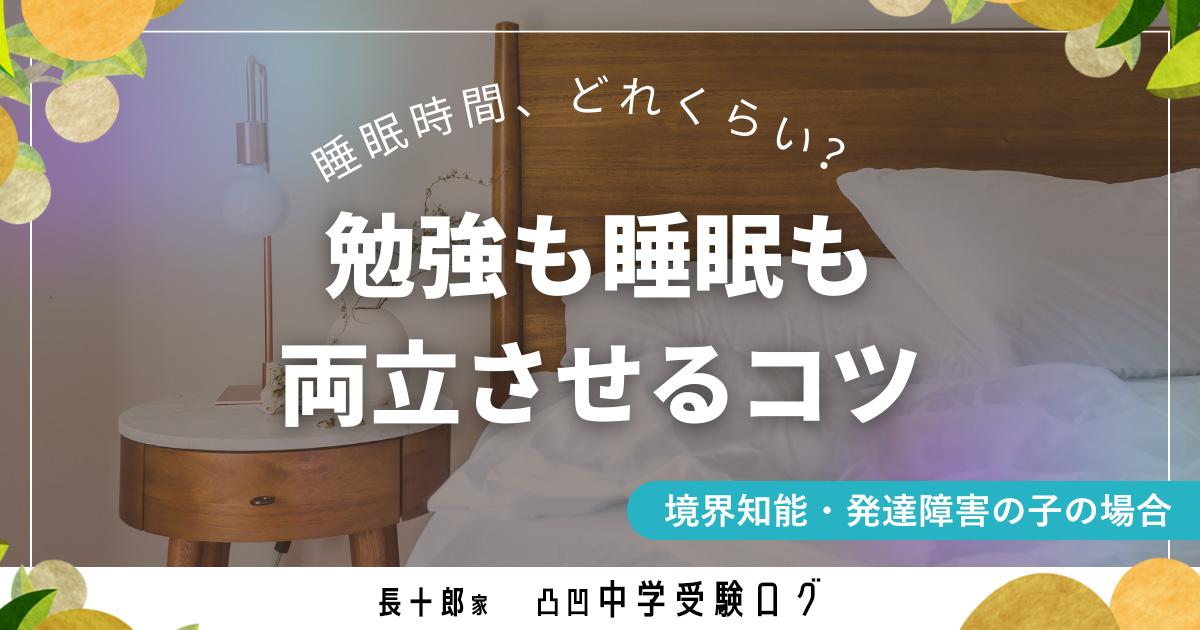中学受験と聞くと、毎日長時間の勉強や生活の制限をイメージする方も多いのではないでしょうか。
でも、地方の中学受験なら首都圏ほど過酷な競争はなく、我が家では「睡眠・遊び・勉強のバランス」を大切にしています。
この記事では、実際に取り入れている生活リズムや学習スタイルを紹介します。
- 22時就寝・7時起床のルールで整えた睡眠習慣
- 平日1時間・休日自由という遊び時間の工夫
- 学習時間を増やさない判断基準と模試を活かした調整法
- バランスを取ることで得られた子どもの変化と家庭の雰囲気の改善
「受験だから遊びは我慢」「勉強時間をとにかく増やす」という考えにとらわれず、家庭ごとに合ったやり方を見つけることが大切です。
我が家のゆるめな中学受験スタイルが、同じ悩みを持つご家庭の参考になればうれしいです。
わが家の睡眠ルール

毎日の生活リズムを安定させるために、睡眠のルールをきちんと決めました。
中学受験といっても地方なので首都圏ほどの過密スケジュールはなく、無理に夜更かしして勉強する必要はないと考えています。
そこで「22時就寝・7時起床」を徹底するようにしました。
実際は21時台に寝ることが多いです
元々小さい頃からしっかり寝る子で21時台に寝る習慣はついていたので、勉強量が増えてきてもここはスムーズに守れています。
22時就寝・7時起床を徹底
平日は学校の後に放課後デイに行っているので家での勉強時間を確保するのが難しくて、なら朝しかない!ということで朝学習を30分取り入れていました。
ただ、よく考えたら我が家の中に朝型人間が誰もいない!
どうりで朝学習が全然はかどらないわけだ…。
もっと早く気づけ
全く続かなかったので結局あきらめて、塾で出される「毎日1ページずつやるタイプのドリル」だけを朝に取り組むようにしています。
起床時間も6時半だったところから7時と余裕が出て、無理なく続けられるようになりました。
「夜は早く寝る」「朝は最低限の学習だけやる」というシンプルな習慣に切り替えたことで、毎日の生活に安定感が出てきました。
睡眠を優先することで、日中の集中力も上がったと感じています。
休日の早起き問題とゲーム・YouTubeの関係
休みの日は勉強よりも遊びがメインになりがちです。
理想としては少し長めに寝てほしいのですが、どうしてもゲームやYouTubeを楽しみたい気持ちから、平日よりも早く起きてしまうことがあります。
そこで我が家では、ただ早起きして遊んでしまわないようにルールを設けています。
ゲーム機には利用時間を設定し、テレビも電源部分にミニプラグを挟んで簡単にはONできないようにしました。
こうすることで、朝早く目が覚めてもすぐに遊びに直行できない仕組みにしています。
この工夫を取り入れてからは、無駄に早起きして睡眠時間を削ることが減り、休みの日でも安定した生活リズムを保てるようになりました。
\ うちで使っているミニプラグはこちら /
スマホからテレビの電源を遠隔操作できる優れもの!タイマー設定とかもできて便利です
遊び時間のルールと管理方法

勉強ばかりに偏るとストレスが溜まり、逆に遊びすぎると勉強が後回しになります。
そのため、我が家では「遊び時間は自由に楽しめるけれど、学習時間も少しずつ増やしていく」というスタンスをとっています。
地方の中学受験なので首都圏ほど過密ではありませんが、子ども自身がどう勉強を進めていきたいかを考えながら、段階的に生活リズムを調整しています。
平日は1時間まで、休日は自由+条件付き
平日の遊び時間は1時間までと決めています。
最初、平日は一切ゲーム・YouTubeはなしにしていたんですが、息子が「毎日ご褒美がほしい」との直談判があり、1時間までOKということに。
無理に長時間勉強させるよりも、少しの遊びでリフレッシュできる方が効果的かもな…と思い、そのまま継続しています。
休日は自由に遊んでOKですが、学習時間を徐々に増やすのが方針です。
現在は平日・休日どちらも1日1時間半程度の勉強ですが、今後は休日を2時間に延ばし、最終的には遊びと勉強が半々になるように慣らしていく予定です。
この予定も息子本人が考えました
ただし、無理に時間を延ばすと疲弊するだけなので、本人の体調ややる気を最優先に。
特に頭痛が起きやすい体質でもあるため、頑張りすぎないよう注意しています。
また、志望校の在校生に話を聞いたところ、6年生のときは1日3時間くらい勉強していたそうです。
その子は特別に優秀で常に100点を取るタイプではなく、普通に努力して合格したとのことでした。
この話を参考にしながら、我が家でも無理なく学習時間を積み上げていこうと考えています。
学習時間を増やさない判断基準

中学受験というと「とにかく勉強時間を増やさなければ」と考えがちですが、我が家ではあえて時間を増やしすぎないようにしています。
理由は、時間を積み重ねるだけでは効果が出にくく、子どもが疲れてしまうから。
塾と模試を軸に「これ以上は必要ない」と判断する基準を持つことで、生活全体のバランスを保てるようになりました。
塾宿題+模試解き直しで十分な理由
我が家では「塾の宿題をきちんとやる」「模試の解き直しをする」の2つを最低ラインにしています。
この2つをこなせれば、一旦次の模試までの勉強は十分と考えています。
塾から出される宿題は、授業内容の定着に直結するものばかりなので言わずもがな必須。
個別塾なのでこなせない量の宿題が出るなんてこともないので、出されたものは確実にやってもらいます。
1回解いたあと翌日に解き直しまでが1セット。後日さらに間違えた問題だけもう一度やってもらうこともあります
加えて模試の解き直しをすると、弱点をピンポイントで補強できるので、時間を増やさなくても効率的に学力がついていきます。
「さらに演習を積みたい」と思うときだけ追加で取り組むくらいがちょうどいい感じですね。
現状模試の解き直し以外は漢検・数検の勉強くらいで、それ以外には手を付けていません。塾で使うテキスト以外を購入する予定もなし。
普段はこれ以上無理に増やさない方が集中力を維持できると感じています。
模試結果を見て調整する柔軟さ
学習時間は固定するのではなく、模試の結果を見ながら柔軟に調整するようにしています。
例えば「算数の特定単元でミスが続いている」と分かれば、その部分だけ重点的に演習を増やす。
逆に安定して点が取れている教科については、必要以上に時間をかけません。
また、子どものやる気や体調も重要な判断材料です。
頭痛が起きやすい体質なので、無理をさせすぎると逆効果になると分かっています。
本人が「もっとやりたい」と感じるときにだけ勉強時間を増やし、そうでないときは前もって決めた時間に潔く切り上げる。
この柔軟さが、長期的に見ると安定した学習習慣につながっています。
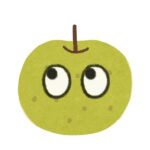 長十郎
長十郎親が無理やり引き延ばそうとするとそのうち信頼してもらえなくなりそう
バランスを取ることで得られた変化

睡眠・遊び・勉強のバランスを意識した生活を続けてきたことで、子どもにも家庭にもいくつかの良い変化がありました。
中学受験に向けての準備は長期戦ですが、生活全体が安定していると無理なく続けられると実感しています。
ストレス軽減と集中力アップ
勉強時間を必要以上に増やさない方針にしてから、子どものストレスが大きく減りました。
遊びの時間があることで気持ちを切り替えやすくなり、机に向かうときの集中力も高まっています。
以前は「やらされている感」が強かった宿題や模試の復習も、今では自分から進んで取り組むことが増えました。
勉強そのものが重荷にならず、生活の一部として自然に取り入れられるようになったのが大きな変化だと思います。
家族の雰囲気が良くなった
「勉強の時間だよ!」「テレビ消して!」と毎日のように言わなくてもよくなり、家庭の雰囲気が穏やかになったなーと感じています。
ルールを決めて、それを親子で納得して守るようにした結果、余計な口出しが減りました。
私のイライラも減ったので子どもに接するときの口調が柔らかくなりました。笑
受験勉強はどうしてもピリピリした空気になりがちですが、我が家の場合は「ゆるめのルール」を設けたことで余裕を持って取り組めています。
このように、バランスを意識することは学力だけでなく、家庭全体の雰囲気を良くする効果もあるんですよね。
勉強は今だけじゃないので、ネガティブな印象を抱かないようにするのも大事だよなと思っています。
大してやる気もないのにガン詰めしたところで失うものも多そうですし、そうしないと受からないのなら公立にお世話になればいいだけのこと、という考えで向き合っています。
頑張りすぎずに合格をもらえたら、より自信を持って進学できそう
まとめ
今回の記事では「中学受験における睡眠・遊び・勉強のバランス」について、我が家の実例を紹介しました。
- 22時就寝・7時起床のリズムを徹底して無理なく継続
- 平日は遊び時間を1時間、休日は自由だが学習時間を段階的に延ばす方針
- 塾宿題と模試の解き直しを最低ラインにし、それ以上は無理に増やさない
- 模試結果や子どもの体調・やる気を見ながら柔軟に調整する
- 結果としてストレスが減り、集中力や家庭の雰囲気も改善
地方の中学受験だからこそ、首都圏のように過密なスケジュールを詰め込む必要はありません。
それよりも「睡眠・遊び・勉強」のバランスを取りながら、少しずつ勉強習慣を積み重ねていくことが合格への近道だと感じています。
この記事を読んでくださった方も、ご家庭の状況やお子さんの個性に合わせて「無理のないバランス」を見つけていただけたら嬉しいです!