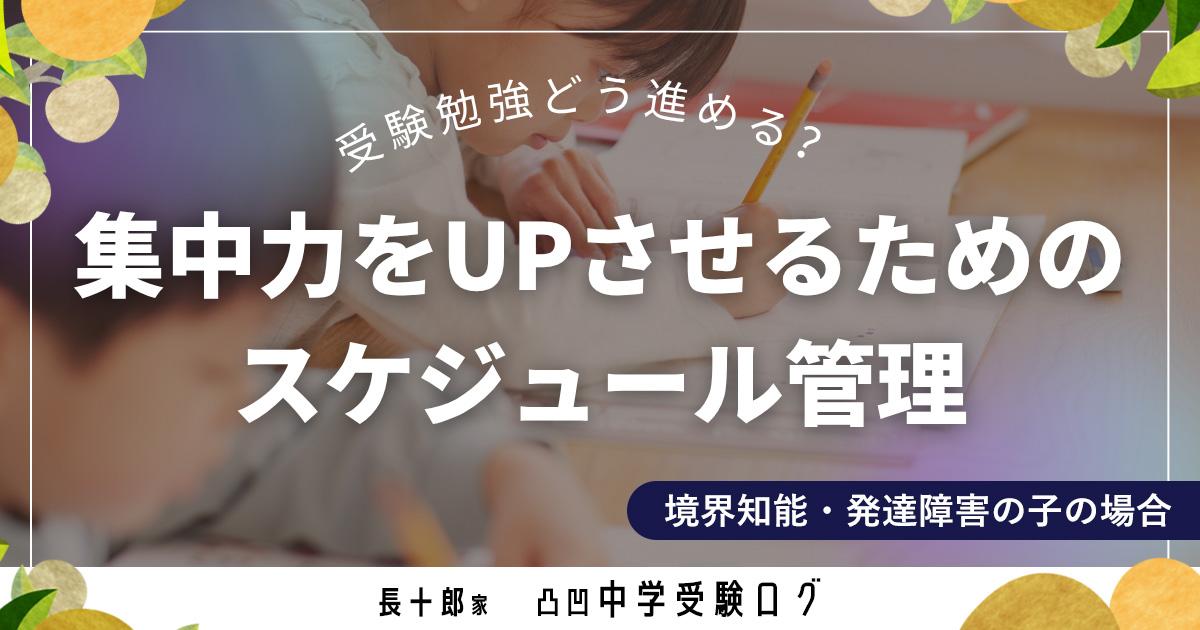「中学受験を考えているけれど、うちの子は集中力が続かない…」
「境界知能や発達障害グレーゾーンの子でも、受験ってできるの?」
そんな悩みを抱えている親御さんに向けて、わが家のリアルな実体験を元に、無理なく進められるスケジュール管理と集中力アップの工夫を紹介します。
- 子どもと相談しながら決めるスケジュールの作り方
- 段階的に学習時間を増やす方法
- レベル別の学習計画でムリなく続ける工夫
- 集中力を育てるために取り入れた3つのポイント
- 親の負担も減らせるオンライン自習室「ヤルッキャ」の活用法
どれも実際に試して「これならうちでもできそう!」と思えた方法ばかりです。
中学受験をあきらめたくない、でも今のままで大丈夫か不安…という方に、少しでも参考になればうれしいです。
親子で決めるスケジュールの基本ルール

中学受験を意識しはじめたとき、最初に悩んだのが「どんな風に学習スケジュールを決めればいいのか?」でした。
わが家では、親が一方的にルールを決めるのではなく、必ず子どもと一緒に相談して決めるようにしています。
ここでは、そんなわが家のスケジュール決めの基本ルールについて、実体験ベースでご紹介します。
押し付けずに相談して決める
我が家では、「こうしなさい」と親が決めるのはなるべく避けています。
たとえば勉強時間を決めるときも、「30分にしようね」ではなく、「30分だとどう?」「お母さんは30分ぐらいがいいかなと思うんだけど」と必ず本人に聞くようにしてます。
親の立場としては、「こうした方がいいよね」と思うことはあるんですが、それを押しつけると反発されるし、続かないんですよね…。
発達ゆっくりな我が家でも高学年に入るとさすがに反発されました
だから「これはお母さんの意見だけど」と前置きしたり、そういうニュアンスを含めて話すようにしています。
「これぐらいならどう?」「ちょっと無理かも…」みたいなやり取りをしながら、本人が納得できるラインを一緒に探します。
もちろん親の希望とズレることもありますが、「自分で決めた」っていう意識があると、勉強に向かうときのスムーズさが違うなと感じてます。
自己責任を持たせるメリット
スケジュールや学習内容を決めるときに「これでやる」と決めたのは自分なんだという感覚がすごく大事だと思っています。
もちろん小学生なので、完璧に責任を持たせるのは無理です。
でも「自分で決めたんだから、やる」って思えるようになるだけで、行動が少し変わってきます。
自分から動いて、その結果、できたときには「自分でやり切った」っていう達成感にもつながります。
反対に、もしうまくいかなくても「じゃあ次どうする?」と考えるきっかけも生まれます。
サポートなしではこの流れはなかなか身に付かないですが、徐々に定着していけばいいなと。
親からの発信ばかりだと、いざ何かできていなかったときに「なんでやってないの!?」ってなりますしね。
子ども発信だと親のストレスもいくらか減ります
いずれ親を頼らず勉強するようになったときに、この積み重ねが活きてくれるといいなと思っています。
小4から始めた段階的な学習時間の増やし方

受験を意識しはじめたのは小4のときでした。
いきなり毎日何時間も勉強するのは絶対に無理だと思ったので、少しずつ時間を増やしていく方向でいくことに。
まずは、学年×10分というルールからスタートした我が家の初期の取り組みについてお話しします。
学年×10分ルールからのスタート
自主学習の時間の目安として、学年×10分ってよく聞きませんか?
学校によっては学年×15分とも言われていますよね。
なので、これを参考にしてまずは1日40分くらいを目標にしてみました。
一気に40分だとちょっと難しいかもと思い朝10分・夜30分にしたところ、特に問題なくこなせるようになりました。
「今日はこれだけやれたね」と一緒にカレンダーにチェックを入れたり、好きなシールを貼ったりして、小さな達成感を積み重ねることを大事にしてました。
ここから少しずつ勉強時間を伸ばしていくことになるんですが、それに伴って家庭の状況や本人の気持ちにもいろいろ変化がありました。
小4→小5での学習時間変化と背景
小4の1年間は、学習習慣をつけることを最優先にして、無理のない範囲で進めていました。
でも小5になると、少しずつ“受験”という言葉が現実味を帯びてきますよね。
わが家でも、小4の終わり頃には1日100分近く勉強する日が出てきて、親としては「おっ、いけるかも」と思っていました。
ただ、実はこの頃に用意していたテキストが息子には難しすぎたんです。
家庭教師から「算数は大問に小問が2つ合って、小問の内容が連動しているものがいい」と言われ探した教材だったんですが、市販で売ってるテキストは1問ずつのやつがほとんどで、見つけられたのはコレ↓のみでした。
\ 国語はこれを使ってました /
いいテキストなんですけど、宿題として自分でやるには難しかったです
首都圏で中受される方には簡単すぎると思いますが、ボリュームゾーン未満の子だったらたぶんこれぐらいがちょうどいい難易度なのかな?
現在塾で使っているテキストも標準レベルですが、宿題用のテキストはもう少し簡単なものになっていて、授業用と宿題用はやはり分けるべきなんだなと実感しました。
授業を一発で完璧に理解できる子ならともかく、そうではないので自信を失わずに授業内容を定着させるためには宿題用のテキスト選びって結構大事だなと。
そのせいか、勉強時間は増えても解けてる問題は決して多くなくて、だんだんと疲れてしまいまして…。
いろいろあって家庭教師の指導に限界を感じて、小5に入ってすぐ個別指導塾に切り替えることに。
塾の宿題をしっかりやることに集中するため、自学の時間はまた1日40分ほどに自然と減りました。
それでも、小4で「毎日机に向かう」という習慣がついていたのは大きな収穫だったことは変わりません。
1日40分やることは当たり前になっていましたし。
ただこれでいいわけではないので、ここからまた、段階的に学習時間を増やしていくことになります。
わが家の「レベル別学習時間」設定法

自主学習の時間を段階的に増やすにあたって、小5の前半から「レベル制」の学習計画を取り入れてみました。
息子に自分で計画を立ててもらって、段階的にレベルアップしていく仕組みにしたことで、ちょっとゲーム感覚もあって我が家には合っていました。
ここでは、我が家で実際に作ったレベル1〜6の設定内容と、その狙いについてお話しします。
レベル1〜6の概要と狙い
このレベル設定は、本人と一緒に話し合いながら決めたものです。
「これならできそう」「これはちょっと無理かも」と感じたことを正直に言ってもらいながら、納得できる形で作りました。
レベルは10回達成したらアップという方式。
ポイントカードを自作してシールをあげていました。
ざっくり言うと、こんな感じ!
ちょっとしたスキマ時間があるとアマプラやYouTubeに流れがちだったので、読書やタイピングなど“学習っぽい”内容に切り替える意識をしてもらいました。
実際は休憩を10分にするのが厳しくて断念。最終的に20分固定にしました。勉強時間は無理なく達成。
結局なかなか起きられず。朝型じゃないことが判明したので無理にやるのはやめました。
今まで30分を1コマとして自宅学習を進めていましたが、この頃から1コマを1時間にした方が集中が途切れず楽なことに気づきました。集中力が少しずつついてきた成果かな。
現在のレベルはここ。ただ問題なく達成できそう。
これが最上位レベル。本人から「キツすぎるかも…」との発言があったので変更するかもしれません。
こんなふうにレベルを分けることで、どのくらいできていて、どこがハードルなのかが分かりやすくなりました。
実際の到達状況とつまずきポイント
レベル制を取り入れたことで、自分の状態を客観的に見られるようになったのはよかったなと思っています。
とはいえ、順調にレベルアップできたわけではなく、やっぱりいくつかの壁がありました。
たとえば、レベル2の「おやつ休憩10分」はどうしても無理でした。
息子のこだわりとして、おやつを食べている間は手持ち無沙汰だから何か動画を見ていたいということだったので、それを呑んで最初は20分、次は10分という風にしようと本人が言っていたのですが、さすがに10分は短すぎたみたいです。
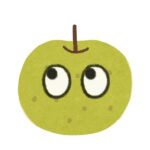 長十郎
長十郎確かに慌ただしい…
なので、ここは「休憩は20分固定でいきますか」とルールを調整しました。
これでもこの目標を立てる前は、おやつを食べ終わってもダラダラ動画を見続けて時間が60分になってしまったり、切り替えがうまくいってなかったんですよね。
あの頃を思えば全然マシ!
まあ20分の目標も、本人がタイマーをかけてはおくものの、私が声をかけないと動画見続けちゃうことがほとんどだったのでストレスではあったんですが、時間になったらテレビを強制的に消せるようガジェットに頼ったら解決しました。
時間を見る癖をつけるのはなかなか特性的に難しいみたいです。もうちょっと大きくなったらこのガジェットの説明して、自分で気を付けられるようになってほしい。
ともあれ文明の利器最高。
それから、レベル3の朝勉も、起きられない&集中できないということで断念。
最初は「朝のうちに終わらせたほうがラクだよ」と話していたけど、合わないなら無理に続けなくてもいいかなと割り切りました。
私も眠いしな…。思えば家族に朝型人間が一人もいないのに無謀でした
息子と似たところの多い夫曰く、「朝はこれからやることがたくさんあるから集中できないし、精一杯頑張る気になれない」とのことでした。
他の中受伴走されている方の記事とか見ると「朝はタイムリミットがあるから集中できる!」というのをめちゃくちゃ見たんですけど、やっぱり人によって向き不向きがありますね。
一方で、レベル4・5の土日学習は順調。
塾に慣れてきたことで、長時間座って勉強することに抵抗がなくなったのが大きかったと思います。
実際に取り組んでみて、どこでつまずくかが分かると、対処もしやすくなるなあという学びがありました。
息子はたまに「あ~レベルが上がってしまう~~!!」と嘆いていますけど。笑
集中力を高めた工夫と気づき

「集中力が続かない」というのは、わが家でもずっと悩みのタネでした。
でも、中学受験を意識するなかで、少しずつ“集中できる時間”を増やしていくための工夫を積み重ねてきました。
それは特別なトレーニングというより、日々の中で「これならできそう」「これは合わないかも」を試していくプロセスだったと思います。
塾の授業で耐久力UP
最初は親と話しながらの30分くらいの勉強でも達成感のある様子だったんですが、塾に通い始めてから少しずつ変わってきました。
90分の授業に慣れてきたことで、「長時間座って問題を解く」ことに抵抗がなくなってきたんです。
さらに、夏期講習で3時間授業を体験したときは、「え、3時間も!?大丈夫かな…」と親の方が心配していましたが、意外と最後まで集中して取り組んでいて驚きました。
最初はうじうじ弱音吐いてましたが、夫から「自然と慣れる」と言われてから暗示がかかったのか次の講習後には「前より時間すぎるの早かった」と言ってました
この頃から、本人も「長く勉強しても意外とできるんだ」と感じたみたいで、自信にもつながっていった気がします。
何より、“塾で集中できた”という成功体験が、家庭学習にもいい影響を与えてくれました。
一人でやる時間を増やすためのヤルッキャ活用
最初の頃は、私がそばにいないと勉強が進まないタイプでした。
なので自然とリビング学習になり、わからない問題が出てくるとすぐ呼ばれたり、「ねえねえ」と関係ない話をしてきたり…。
正直私も疲れるし、子どもの学習時間が増えるほど私の拘束時間も増えるというジレンマ。
でも塾に通い始めて、「一人で解いていくスタイル」に少しずつ慣れてきたことで、家でも“そばにいなくても大丈夫”になってきました。
特に助けになったのが「ヤルッキャ」というオンライン自習室です。
リビング学習でもヤルッキャは使っていたのですが、本来は子どもの自習に使うもの。
いよいよこのサービスの本領を発揮してもらうときがきました
別室で私が仕事をしていても、ヤルッキャが子どもの勉強の様子をLINEで送ってくれる。
「さっきちゃんと勉強してたんだな」という様子が見えるので、安心感がありました。
それに、親がそばにいると「わからない」とすぐ頼ってしまったり、「何問かごとに丸付けしてもらわないと先に進む気にならない」ことがあったりしたのですが、離れていると「自分で考えてみるか」「とりあえず飛ばそう」と意識するようになったんです。
夜、子どもが寝た後にその日の課題をまとめて丸つけするというサイクルにも慣れてきて、私の負担もぐんと減りました。
ヤルッキャのようなツールを使うことで、物理的に距離を取っても見守れるのはすごくありがたかったです。
ヤルッキャについて書いた記事もあるので、もしよければご覧ください。

「短時間×複数回」から「まとめて一気に」への切り替え
以前は、「集中力が続かないから、短く何回かに分けてやろう」と思って、30分×2回みたいなスケジュールを組んでいました。
でもこれ、意外と疲れるんですよね。
1回終わるたびに気が抜けて、次の時間にもう一度エンジンをかけ直すのが親子共々しんどくて。
たとえば13時に30分、15時に30分って設定しても、その間に遊びや動画を挟むと、再び勉強モードに戻るのがすごく難しい。
それよりも、13時〜14時で1時間まとめてやってしまう方が、むしろ集中しやすいことに気づきました。
「やるときは一気にやる。終わったらしっかり休む」っていうシンプルなスタイルが、ようやくマッチするくらい成長したんだなと感じました。
小5の夏にこのやり方に変えてからは、メリハリがついて勉強時間の質も上がった感じがします。
もうちょっと早く気づきたかったけどな…!
まとめ
今回の記事ではこんなことを書きました。
- 子どもが自分で決めることで、勉強に対する責任感ややる気が育つ
- レベル別の学習時間設定で無理なく成長
- うまくいかない部分も柔軟に調整しながら進めた
- 塾や夏期講習が集中力アップのきっかけに
- 親がそばにいなくても集中できる仕組みとして「ヤルッキャ」が有効
- 「短時間を何度も」より「まとめて一気に」の方が効率的だった
受験勉強は、親子で一緒に考え、試行錯誤しながら進めていくものなんですね、やっぱり。
今回紹介した内容が、少しでも同じような悩みを抱えるご家庭のヒントになればうれしいです。